2010年09月14日
京の菜時記(伏見甘長)
京の菜時記、第8回目。
月一回の発行で、本日載せる記事は8月号でしょうか。。
============================================================================
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、8回目となります今回は、伏見とうがらしをご紹介します。
トウガラシは、熱帯アメリカ原産で約6000年前の遺跡から出土するなど相当昔から食されていたようです。日本には、豊臣秀吉の時代に朝鮮半島から伝わり、その当時「高麗胡椒(コショウ)」と呼んでいたという説と、ポルトガル人がブラジルより日本にもたらしたという説もあるようですが、いずれにしても同時代に日本に広まったと考えられています。ただ、その頃に伝来したトウガラシは「胡椒」の名でもわかるように香辛料として用途されていたようで、江戸時代に全国各地作られるようになってもなお辛味の強いものでした。
また、唐辛子と同じ仲間ながら辛味のまったくないピーマンは未だその頃には日本になかったといわれています。
そんな全国各地で作られるようになったトウガラシの中の一つに、伏見とうがらしは生まれました。「雍州府志」(1684)に山城の稲荷付近で作られていたと記載があり、それ以前より京都伏見辺りで栽培されており、その地名をとって「伏見とうがらし」と名づけられました。別名「伏見甘長とうがらし」と呼ばれるように、形状は細長く10cm~20cm近いものもあり、辛味はありません。(何度も食していますが、辛いものに当たったことがありません。)焼いて少し焦げ目を付け、醤油で食べるのが一般的ですが、天ぷらにしても、葉とともにちりめん雑魚と炊いて佃煮風にしても美味しくいただけます。
今のように京野菜ブランドが確立する以前は作付面積が減る一方で、出荷量も少なくなりましたが、今では京都府域各地で栽培されており、ハウス等の施設栽培によって年間通じて食べることができるようになりました。ですが、旬の時期としてはやはり夏(6月~8月)。冬の寒い時期に暖房を焚いたハウス内で栽培されるモノを食べるよりも、自然の太陽の光を直接浴びた路地モノが出回る今の時期をお勧めします。施設栽培では、流通量に限りがありコストがかかるため価格が高くなりがちです。
食物繊維・カルシウム等が豊富で夏バテ防止の京野菜ですので、是非どうぞ。

================================================================================
上鳥羽の生産者が作る京野菜の情報をご希望の方は、ぜひご連絡ください。
なお、情報は不定期に発送するものです。ご希望によってDMもしくはFAX、またはメール、電話。
お問合せはこちらから
TEL/FAX 075-693-6757
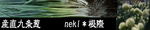
月一回の発行で、本日載せる記事は8月号でしょうか。。
============================================================================
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、8回目となります今回は、伏見とうがらしをご紹介します。
トウガラシは、熱帯アメリカ原産で約6000年前の遺跡から出土するなど相当昔から食されていたようです。日本には、豊臣秀吉の時代に朝鮮半島から伝わり、その当時「高麗胡椒(コショウ)」と呼んでいたという説と、ポルトガル人がブラジルより日本にもたらしたという説もあるようですが、いずれにしても同時代に日本に広まったと考えられています。ただ、その頃に伝来したトウガラシは「胡椒」の名でもわかるように香辛料として用途されていたようで、江戸時代に全国各地作られるようになってもなお辛味の強いものでした。
また、唐辛子と同じ仲間ながら辛味のまったくないピーマンは未だその頃には日本になかったといわれています。
そんな全国各地で作られるようになったトウガラシの中の一つに、伏見とうがらしは生まれました。「雍州府志」(1684)に山城の稲荷付近で作られていたと記載があり、それ以前より京都伏見辺りで栽培されており、その地名をとって「伏見とうがらし」と名づけられました。別名「伏見甘長とうがらし」と呼ばれるように、形状は細長く10cm~20cm近いものもあり、辛味はありません。(何度も食していますが、辛いものに当たったことがありません。)焼いて少し焦げ目を付け、醤油で食べるのが一般的ですが、天ぷらにしても、葉とともにちりめん雑魚と炊いて佃煮風にしても美味しくいただけます。
今のように京野菜ブランドが確立する以前は作付面積が減る一方で、出荷量も少なくなりましたが、今では京都府域各地で栽培されており、ハウス等の施設栽培によって年間通じて食べることができるようになりました。ですが、旬の時期としてはやはり夏(6月~8月)。冬の寒い時期に暖房を焚いたハウス内で栽培されるモノを食べるよりも、自然の太陽の光を直接浴びた路地モノが出回る今の時期をお勧めします。施設栽培では、流通量に限りがありコストがかかるため価格が高くなりがちです。
食物繊維・カルシウム等が豊富で夏バテ防止の京野菜ですので、是非どうぞ。

================================================================================
上鳥羽の生産者が作る京野菜の情報をご希望の方は、ぜひご連絡ください。
なお、情報は不定期に発送するものです。ご希望によってDMもしくはFAX、またはメール、電話。
お問合せはこちらから
TEL/FAX 075-693-6757
2010年09月13日
京の菜時記(賀茂茄子)
京の菜時記
油断をしていたら、時期がずれてしまいました。
もうすぐ終わりですが、この野菜を・・・・
=============================================================
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、7回目となります今回は、京野菜を代表する野菜、賀茂茄子をご紹介します。
賀茂茄子の起源については明らかではありませんが、1684年刊行の「雍州府志」という書物に洛東河原において栽培していた丸くて大きい茄子という記述があり、これが賀茂茄子だといわれています。栽培の上で多量の水を要すため、水利に恵まれた地区が産地となり、京都市内では上賀茂・西賀茂周辺が主な産地です。現在では、京都府綾部市や亀岡市でも盛んに栽培されています。ただ、市場価格・店頭価格について、京都産は少々高くなっております。近畿圏では、奈良県でも丸茄子として出荷されており、京都の量販店でも購入することができます。
手にあまる大きさで、直径は15cm、重さは1k近くあるものも。ですが、近年は比較的小さなものが多くなっています。というのにもわけがあり、料理店にあっては、あまりに大きな賀茂茄子を懐石料理の一つとして出すと、それ一つでお腹がいっぱいになってしまう。また、スーパー等の量販店からも小さいほうが消費者に手ごろ感があるとのことで、綾部市や亀岡市の賀茂茄子は比較的小さめのサイズを多くなっています。一方、昔からの産地である上賀茂・西賀茂の生産者の方は、賀茂茄子にはこのズッシリ感がないと・・・とおっしゃられ、見事なまでの大きくて立派な賀茂茄子を作られておられます。茄子は、1本の木から数十本が収穫できますが、賀茂茄子は花を落とし選定する作業に手間がかかります。大きなものを作るにはなおの事、一つの実に栄養分を集中させるためにもったいないと思えるほど選定し、花のうちに落としてしまいます。そのようにして、立派な賀茂茄子が収穫されるのです。
賀茂茄子には、「三ヘタ」といって三角形のヘタが特徴で、またそこには大きなトゲがあり、そのトゲに触れると痛いこと。表面を覆う皮は柔らかく、キズがつければそこから傷みはじめるために、収穫・出荷には細心の注意が必要です。
上賀茂の生産者といえば、昔ながらの振り売りで有名です。今でも多品目の野菜を売りに回っておられます。そのために、京都市産に限れば市場を介しての流通量は極端に少なく、また貴重な野菜といえます。

===================================================================
上鳥羽の生産者が作る京野菜の情報をご希望の方は、ぜひご連絡ください。
なお、情報は不定期に発送するものです。ご希望によってDMもしくはFAX、またはメール、電話。
お問合せはこちらから
TEL/FAX 075-693-6757
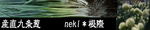
油断をしていたら、時期がずれてしまいました。
もうすぐ終わりですが、この野菜を・・・・
=============================================================
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、7回目となります今回は、京野菜を代表する野菜、賀茂茄子をご紹介します。
賀茂茄子の起源については明らかではありませんが、1684年刊行の「雍州府志」という書物に洛東河原において栽培していた丸くて大きい茄子という記述があり、これが賀茂茄子だといわれています。栽培の上で多量の水を要すため、水利に恵まれた地区が産地となり、京都市内では上賀茂・西賀茂周辺が主な産地です。現在では、京都府綾部市や亀岡市でも盛んに栽培されています。ただ、市場価格・店頭価格について、京都産は少々高くなっております。近畿圏では、奈良県でも丸茄子として出荷されており、京都の量販店でも購入することができます。
手にあまる大きさで、直径は15cm、重さは1k近くあるものも。ですが、近年は比較的小さなものが多くなっています。というのにもわけがあり、料理店にあっては、あまりに大きな賀茂茄子を懐石料理の一つとして出すと、それ一つでお腹がいっぱいになってしまう。また、スーパー等の量販店からも小さいほうが消費者に手ごろ感があるとのことで、綾部市や亀岡市の賀茂茄子は比較的小さめのサイズを多くなっています。一方、昔からの産地である上賀茂・西賀茂の生産者の方は、賀茂茄子にはこのズッシリ感がないと・・・とおっしゃられ、見事なまでの大きくて立派な賀茂茄子を作られておられます。茄子は、1本の木から数十本が収穫できますが、賀茂茄子は花を落とし選定する作業に手間がかかります。大きなものを作るにはなおの事、一つの実に栄養分を集中させるためにもったいないと思えるほど選定し、花のうちに落としてしまいます。そのようにして、立派な賀茂茄子が収穫されるのです。
賀茂茄子には、「三ヘタ」といって三角形のヘタが特徴で、またそこには大きなトゲがあり、そのトゲに触れると痛いこと。表面を覆う皮は柔らかく、キズがつければそこから傷みはじめるために、収穫・出荷には細心の注意が必要です。
上賀茂の生産者といえば、昔ながらの振り売りで有名です。今でも多品目の野菜を売りに回っておられます。そのために、京都市産に限れば市場を介しての流通量は極端に少なく、また貴重な野菜といえます。

===================================================================
上鳥羽の生産者が作る京野菜の情報をご希望の方は、ぜひご連絡ください。
なお、情報は不定期に発送するものです。ご希望によってDMもしくはFAX、またはメール、電話。
お問合せはこちらから
TEL/FAX 075-693-6757
2010年05月15日
京の菜時記(豌豆)
京の菜時記・・・
今の季節にぴったりの菜時記です。。。
===========================================================
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、6回目となります今回、京野菜として指定されているわけではありませんが、ぜひ地場のものを食べていただきたいというそんな新緑の季節にふさわしい野菜をご紹介。
さて、春の旬野菜といえば前回ご紹介した筍ですが、月が替わって初夏の雰囲気が漂う季節になると味わっていただきたい野菜といえば豌豆(えんどう)豆です。えんどう豆といえば和歌山県のうすいえんどうが有名ですが、実は京都でも各地で作られています。
えんどう豆は、11月に種を蒔き、芽を吊り上げ、網を張り、花を咲かせて実を収穫します。収穫するまでの工程が多く、また収穫まで半年かかり、生産者にとっては手間隙かかる野菜の一つです。また、収穫作業も蔓(つる)が絡み合った中から実だけを刈り取るために、収穫するたびに蔓(つる)を傷つけることとなり、何度も収穫するというわけにはいきません。実が大きくふくらんだ鞘を見つけて刈り取る作業だけでも手間のかかる作業です。
どんな野菜でもそうなのですが、そのように手間隙かけて収穫したえんどう豆の香りと味をいえば、生産者にとっても大変嬉しく季節を感じさせてくれる野菜です。また、時間が経てば皮が硬くなり香りも落ちます。収穫時よりできる限り早く食べることができる地場のえんどう豆がお勧めです。地場のえんどう豆を「地の豆(ジのマメ)」といいます。収穫したての豆がそれだけ美味しいことを意味します。
京都で農業を営まれている生産者であれば、ほとんどの方が自家消費用としてえんどう豆を作られています。スーパー等に並んでいるえんどう豆も美味しいとは思いますが、最近は畑の横でちょっとした直売をされている生産者もたくさんおられますので、ぜひそちらをご賞味ください。
えんどう豆といえば「豆ごはん」を連想されることと思いますが、同じく5月に旬を迎える京都のキャベツ(別名:甘藍)と一緒に炊いて食べると、より初夏を感じることができます。キャベツの甘みとえんどう豆の何ともいえない香り・・・、薄皮がはじけて中からジワッとにじみ出てくる豆本来の旨みが絶妙です。
えんどう豆の旬は、5月のみ。収穫時に蔓(ツル)を傷つけるために何度も収穫できません。どんな野菜でもそうなのですが、1年のうちで「今の時期」という旬な野菜をぜひご賞味ください。

===========================================================
上鳥羽の生産者も自家消費用で豌豆は作られています。
もう少し・・・かな。
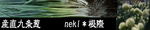
今の季節にぴったりの菜時記です。。。
===========================================================
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、6回目となります今回、京野菜として指定されているわけではありませんが、ぜひ地場のものを食べていただきたいというそんな新緑の季節にふさわしい野菜をご紹介。
さて、春の旬野菜といえば前回ご紹介した筍ですが、月が替わって初夏の雰囲気が漂う季節になると味わっていただきたい野菜といえば豌豆(えんどう)豆です。えんどう豆といえば和歌山県のうすいえんどうが有名ですが、実は京都でも各地で作られています。
えんどう豆は、11月に種を蒔き、芽を吊り上げ、網を張り、花を咲かせて実を収穫します。収穫するまでの工程が多く、また収穫まで半年かかり、生産者にとっては手間隙かかる野菜の一つです。また、収穫作業も蔓(つる)が絡み合った中から実だけを刈り取るために、収穫するたびに蔓(つる)を傷つけることとなり、何度も収穫するというわけにはいきません。実が大きくふくらんだ鞘を見つけて刈り取る作業だけでも手間のかかる作業です。
どんな野菜でもそうなのですが、そのように手間隙かけて収穫したえんどう豆の香りと味をいえば、生産者にとっても大変嬉しく季節を感じさせてくれる野菜です。また、時間が経てば皮が硬くなり香りも落ちます。収穫時よりできる限り早く食べることができる地場のえんどう豆がお勧めです。地場のえんどう豆を「地の豆(ジのマメ)」といいます。収穫したての豆がそれだけ美味しいことを意味します。
京都で農業を営まれている生産者であれば、ほとんどの方が自家消費用としてえんどう豆を作られています。スーパー等に並んでいるえんどう豆も美味しいとは思いますが、最近は畑の横でちょっとした直売をされている生産者もたくさんおられますので、ぜひそちらをご賞味ください。
えんどう豆といえば「豆ごはん」を連想されることと思いますが、同じく5月に旬を迎える京都のキャベツ(別名:甘藍)と一緒に炊いて食べると、より初夏を感じることができます。キャベツの甘みとえんどう豆の何ともいえない香り・・・、薄皮がはじけて中からジワッとにじみ出てくる豆本来の旨みが絶妙です。
えんどう豆の旬は、5月のみ。収穫時に蔓(ツル)を傷つけるために何度も収穫できません。どんな野菜でもそうなのですが、1年のうちで「今の時期」という旬な野菜をぜひご賞味ください。

===========================================================
上鳥羽の生産者も自家消費用で豌豆は作られています。
もう少し・・・かな。
2010年03月13日
京の菜時記~筍~
このままいけば、少し季節を追い越す感はありますが、筍の菜時記を・・・・。
**************************
京の菜時記 (筍)
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、今回は春を代表する野菜としてあまりにも有名な「京たけのこ」を紹介します。
さて、春の味覚といえば「筍」。筍は名前の通り「竹の子」ですが一般的には「孟宗竹」という種類を食します。孟宗竹は中国から伝来したもので、その時期等については諸説あります。800年代に京都府長岡京市にある寂照院の開祖が唐から持ち帰り植えたという説があり、境内の入り口には「日本孟宗竹発祥の地」の石碑が建っています。
筍そのものは全国各地で作られていますが、京都の筍は、光るような白さと軟らかさ、そして何ともいえない独特の風味が特徴で、それらは毎年行われる「土入れ」「敷わら」という生産者の努力の賜物でもあり、長年の経験を要するものでもあります。
筍は当然のことながら竹林で栽培します。「土入れ」と一言でいってもその作業は大変なもので、足場の悪い竹林を、土をいっぱいにもった手押し車で何度も何度も往復するという極めて大変な作業です。また収穫時は、地表から芽をだしてしまうと色がすぐに変わってしまうために、竹林中を歩いて周り、地表に出ていない芽を見つけるという相当な経験と、折れないように細心の注意を払い筍掘り専用の鍬をつかっての収穫するという熟練された技が必要なのです。
京都では、皮の色が白く軟らかい筍を「シロコ」といいます。「シロコ」は皮が薄くて肉質柔らか、市場評価も極めて高く、まさしく「これぞ、京たけのこ」です。京都では盆地を囲む各地の竹林で栽培はされていますが、「京たけのこ」の代表産地といえば、京都西山一帯(長岡京、乙訓、大原野等)が特に有名です。西山一帯では、今の時期は各地で朝掘り筍の直売がされており、春の味覚を味わおうとどこも盛況です。
筍料理といえば、ワカメとあっさりと炊いて筍の風味を引き立てる「若竹煮」。ワカメのとろとろ感と筍の歯ごたえ、ほのかに香ばしい香りが独特です。また、新鮮な筍は刺身としてわさび醤油で食べるのも粋なもの。筍御飯と筍づくしはいかがですか?

**************************
http://kyoyasai.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=424581&csid=1
京にんじん も販売しています。
京都の分葱ご入用でしたらご連絡を・・・。
もちろん、九条ねぎ・みず菜ももちろんあります・・・。
・・・っと、みず菜は終了しました。。
京筍は、市場仕入れで対応できます。
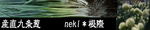
**************************
京の菜時記 (筍)
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、今回は春を代表する野菜としてあまりにも有名な「京たけのこ」を紹介します。
さて、春の味覚といえば「筍」。筍は名前の通り「竹の子」ですが一般的には「孟宗竹」という種類を食します。孟宗竹は中国から伝来したもので、その時期等については諸説あります。800年代に京都府長岡京市にある寂照院の開祖が唐から持ち帰り植えたという説があり、境内の入り口には「日本孟宗竹発祥の地」の石碑が建っています。
筍そのものは全国各地で作られていますが、京都の筍は、光るような白さと軟らかさ、そして何ともいえない独特の風味が特徴で、それらは毎年行われる「土入れ」「敷わら」という生産者の努力の賜物でもあり、長年の経験を要するものでもあります。
筍は当然のことながら竹林で栽培します。「土入れ」と一言でいってもその作業は大変なもので、足場の悪い竹林を、土をいっぱいにもった手押し車で何度も何度も往復するという極めて大変な作業です。また収穫時は、地表から芽をだしてしまうと色がすぐに変わってしまうために、竹林中を歩いて周り、地表に出ていない芽を見つけるという相当な経験と、折れないように細心の注意を払い筍掘り専用の鍬をつかっての収穫するという熟練された技が必要なのです。
京都では、皮の色が白く軟らかい筍を「シロコ」といいます。「シロコ」は皮が薄くて肉質柔らか、市場評価も極めて高く、まさしく「これぞ、京たけのこ」です。京都では盆地を囲む各地の竹林で栽培はされていますが、「京たけのこ」の代表産地といえば、京都西山一帯(長岡京、乙訓、大原野等)が特に有名です。西山一帯では、今の時期は各地で朝掘り筍の直売がされており、春の味覚を味わおうとどこも盛況です。
筍料理といえば、ワカメとあっさりと炊いて筍の風味を引き立てる「若竹煮」。ワカメのとろとろ感と筍の歯ごたえ、ほのかに香ばしい香りが独特です。また、新鮮な筍は刺身としてわさび醤油で食べるのも粋なもの。筍御飯と筍づくしはいかがですか?

**************************
http://kyoyasai.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=424581&csid=1
京にんじん も販売しています。
京都の分葱ご入用でしたらご連絡を・・・。
もちろん、九条ねぎ・みず菜ももちろんあります・・・。
・・・っと、みず菜は終了しました。。
京筍は、市場仕入れで対応できます。
2010年03月03日
京の菜時記 (分葱)
京の菜時記、4回目に投稿した記事は今の時期にピッタリのこの野菜。
「分葱」です。
「九条ねぎと何が違うの?」
という質問も聞こえそうですが、まったく別物です。
・・・といってしまえばそれまでですが、ねぎと違い分けつが非常に多く、成長がすぎると茎(?)が太くなるのではなく、らっきょうが張ります。
また、分葱といえば「てっぱい」(白味噌和え)ですが、九条ねぎとは食感がまったく違います。
個人的には、「てっぱい」はやはり「分葱」です。
**************************
京の菜時記 (分葱)
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、前回に引き続き今回も春の野菜をご紹介。
さて、今回は一般的にいう「京野菜」のご紹介ではありません。でも、京都産となるとこの春先の短い期間しか流通しない貴重な野菜のご紹介です。それは「分葱(ワケギ)」。全国的には広島県が最も生産量が多いそうですが、京都でも作付けされ出荷されています。京都では春先の今の時期に出荷のピークを迎えます。
分葱と聞かれてどんな料理を思い浮べますか?分葱といえば皆さん口をそろえておっしゃるのが「てっぱい」です。その語源は「鉄砲和え」がなまったものらしいのですが、わかりません。てっぱいそのものは讃岐地方の伝統料理で香川県では「フナ」を入れるようです。地域・・・家庭・・・それぞれに入れる具材は違うかと思いますが、私の家では・・白味噌と白ゴマ・・・それにイカと火にあぶった油揚げ、そして分葱。分葱の変わりに春に出回る若葱を使うこともありますが、葱より明らかに柔らかくシャキッという食感は分葱ならではのものです。
分葱と九条葱(特に、春に出回る若葱)は一見すると同じようにみえますが、まったくの別物。春の陽射しをうけてどんどんと太く長く成長する九条ねぎに対して、分葱は根に養分を溜め込みます。つまり、らっきょが大きくなるのです。
春先に出始める分葱・・・暖かい日が続くと一気にらっきょがはり、たちまち出荷できる状態ではなくなります。生産者にとっては赤葉の掃除がやりにくくなり、束にする作業がやりにくくなり、見た目にも悪く出荷を取りやめるということになるのです。
上のような事情から京都産の分葱の出荷は約1ヶ月程度。2月下旬から出始めますが寒冷遮をかけて出荷を早めているものです。暖かい日が続くと酢味噌の効いたサッパリとした「分葱のてっぱい」・・・食べたくなりませんか?
ぜひ、ご賞味あれ。

**************************
http://kyoyasai.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=424581&csid=1
京にんじん も販売しています。
京都の分葱ご入用でしたらご連絡を・・・。
もちろん、九条ねぎ・みず菜ももちろんあります・・・。
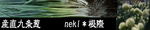
「分葱」です。
「九条ねぎと何が違うの?」
という質問も聞こえそうですが、まったく別物です。
・・・といってしまえばそれまでですが、ねぎと違い分けつが非常に多く、成長がすぎると茎(?)が太くなるのではなく、らっきょうが張ります。
また、分葱といえば「てっぱい」(白味噌和え)ですが、九条ねぎとは食感がまったく違います。
個人的には、「てっぱい」はやはり「分葱」です。
**************************
京の菜時記 (分葱)
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、前回に引き続き今回も春の野菜をご紹介。
さて、今回は一般的にいう「京野菜」のご紹介ではありません。でも、京都産となるとこの春先の短い期間しか流通しない貴重な野菜のご紹介です。それは「分葱(ワケギ)」。全国的には広島県が最も生産量が多いそうですが、京都でも作付けされ出荷されています。京都では春先の今の時期に出荷のピークを迎えます。
分葱と聞かれてどんな料理を思い浮べますか?分葱といえば皆さん口をそろえておっしゃるのが「てっぱい」です。その語源は「鉄砲和え」がなまったものらしいのですが、わかりません。てっぱいそのものは讃岐地方の伝統料理で香川県では「フナ」を入れるようです。地域・・・家庭・・・それぞれに入れる具材は違うかと思いますが、私の家では・・白味噌と白ゴマ・・・それにイカと火にあぶった油揚げ、そして分葱。分葱の変わりに春に出回る若葱を使うこともありますが、葱より明らかに柔らかくシャキッという食感は分葱ならではのものです。
分葱と九条葱(特に、春に出回る若葱)は一見すると同じようにみえますが、まったくの別物。春の陽射しをうけてどんどんと太く長く成長する九条ねぎに対して、分葱は根に養分を溜め込みます。つまり、らっきょが大きくなるのです。
春先に出始める分葱・・・暖かい日が続くと一気にらっきょがはり、たちまち出荷できる状態ではなくなります。生産者にとっては赤葉の掃除がやりにくくなり、束にする作業がやりにくくなり、見た目にも悪く出荷を取りやめるということになるのです。
上のような事情から京都産の分葱の出荷は約1ヶ月程度。2月下旬から出始めますが寒冷遮をかけて出荷を早めているものです。暖かい日が続くと酢味噌の効いたサッパリとした「分葱のてっぱい」・・・食べたくなりませんか?
ぜひ、ご賞味あれ。

**************************
http://kyoyasai.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=424581&csid=1
京にんじん も販売しています。
京都の分葱ご入用でしたらご連絡を・・・。
もちろん、九条ねぎ・みず菜ももちろんあります・・・。
2010年02月27日
京の菜時記(花菜)
さてさて、京の菜時記・・・春に突入です。
京都中央市場でも入荷量・販売量ともに多くなっています。
でも、これだけ暖かいと「花が咲いてしまう」と気遣いも必要です。。
**************************
京の菜時記 (花菜)
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、今回で三回目、季節も春になり京を彩る野菜たちも春野菜に変わっています。
さて、今回は春・・・のイメージが強いですが、実は冬中出荷されているというそんな野菜をご紹介。名前からも春らしい・・・「花菜」です。別名は「伏見寒咲ナタネ」といい、今のように野菜として食べられるようになる前は正月用の切花として栽培されていました。それがいつの時代からか食用として栽培されるようになったようです。「寒咲」という名のごとく寒い冬の間でも花は咲き、出荷時期になると花菜生産者は摘み取り作業に大忙しです。
出荷の時期は11月上旬から3月中旬で、「花菜」という名前から春の野菜というイメージが強いものの、現在の出荷のピークは2月~3月で一冬出荷できるのですがそのイメージにあわせてか、春先出荷をめがけて作付けされているようです。この記事を読んでいただいている頃には、すでに店頭に並んでいないということも・・・。そのときは来シーズンをお楽しみに。
一般的に冬の野菜は寒い気候に耐えるために自分で甘さを蓄えます。そのため、冬の野菜が美味しいといわれます。実際に冬の大根は瑞々しく、白才やキャベツは甘みがあります。一方、花菜はというと、口の中で広がる独特の苦味が特徴で、甘い野菜ばかりのなかで暖まった胃を刺激します。味だけでなく見た目にも、湯通しすることで、色鮮やかな緑色のなかにつぼみの隙間から黄色の花びらが少し顔をのぞかせ、いかにも春らしい料理に仕上がります。
そういうところから、どうしても春をイメージしてしまう野菜です。実際に、京料理のお店などでは、冬の真っ白な蕪から、春の筍、花菜と季節の移り変わりを目でも楽しませてくれます。
ただ、考えてみると花菜は菜の花のつぼみを食べる野菜。寒咲とはいえ花が咲いてしまう春になれば開花してしまい、食べられないのも当然なのかもわかりません。

**************************
http://kyoyasai.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=424581&csid=1
京にんじん も販売しています。
からし菜ご入用でしたらご連絡を・・・。
もちろん、九条ねぎ・みず菜ももちろんあります・・・。
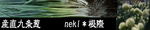
京都中央市場でも入荷量・販売量ともに多くなっています。
でも、これだけ暖かいと「花が咲いてしまう」と気遣いも必要です。。
**************************
京の菜時記 (花菜)
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、今回で三回目、季節も春になり京を彩る野菜たちも春野菜に変わっています。
さて、今回は春・・・のイメージが強いですが、実は冬中出荷されているというそんな野菜をご紹介。名前からも春らしい・・・「花菜」です。別名は「伏見寒咲ナタネ」といい、今のように野菜として食べられるようになる前は正月用の切花として栽培されていました。それがいつの時代からか食用として栽培されるようになったようです。「寒咲」という名のごとく寒い冬の間でも花は咲き、出荷時期になると花菜生産者は摘み取り作業に大忙しです。
出荷の時期は11月上旬から3月中旬で、「花菜」という名前から春の野菜というイメージが強いものの、現在の出荷のピークは2月~3月で一冬出荷できるのですがそのイメージにあわせてか、春先出荷をめがけて作付けされているようです。この記事を読んでいただいている頃には、すでに店頭に並んでいないということも・・・。そのときは来シーズンをお楽しみに。
一般的に冬の野菜は寒い気候に耐えるために自分で甘さを蓄えます。そのため、冬の野菜が美味しいといわれます。実際に冬の大根は瑞々しく、白才やキャベツは甘みがあります。一方、花菜はというと、口の中で広がる独特の苦味が特徴で、甘い野菜ばかりのなかで暖まった胃を刺激します。味だけでなく見た目にも、湯通しすることで、色鮮やかな緑色のなかにつぼみの隙間から黄色の花びらが少し顔をのぞかせ、いかにも春らしい料理に仕上がります。
そういうところから、どうしても春をイメージしてしまう野菜です。実際に、京料理のお店などでは、冬の真っ白な蕪から、春の筍、花菜と季節の移り変わりを目でも楽しませてくれます。
ただ、考えてみると花菜は菜の花のつぼみを食べる野菜。寒咲とはいえ花が咲いてしまう春になれば開花してしまい、食べられないのも当然なのかもわかりません。

**************************
http://kyoyasai.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=424581&csid=1
京にんじん も販売しています。
からし菜ご入用でしたらご連絡を・・・。
もちろん、九条ねぎ・みず菜ももちろんあります・・・。
2010年02月24日
京の菜時記 (畑菜)
さて、昨日の記事にUPしたように今日も私が参加している任意団体(はあとメール)に投稿している記事をUPします。
今回は第2回目。
1月に書いた記事ですが、紹介しているモノは「畑菜」です。^^
そう、京都では「初午」のときに食べる野菜です。
このブログでも取り上げています。。
⇒http://kyoyasai.seesaa.net/article/83112638.html
⇒http://kyoyasai.seesaa.net/article/83452943.html
では・・・・
**************************
京の菜時記 (畑菜)
みなさん、おめでとうございます。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、今回で二回目となります。さて、今回ご紹介する野菜は少し珍しい葉モノ野菜・・・「畑菜」です。
そもそも菜種油をとるために栽培されてきた京都の冬の代表的な葉モノ野菜ですが、なぜ一月の新年号に畑菜を紹介させていただくかというと、わけがございます。一年で畑菜を最もよく食べるという日あるのです。それが今年は二月六日。是非、その日に畑菜を食べていただきたく、一月の今号にご紹介させていただきます。
さて、みなさん、伏見稲荷神社をご存知でしょうか。全国の稲荷神社の総本社としてあまりにも有名な伏見稲荷大社ですが、二月の最初の午の日に行われる行事があるのです。それが、「初午大祭」。和銅四年(711年)、稲荷山の三ヶ峰に稲荷大神が初めてご鎮座された日が、二月の初午の日・・・といわれており、「初午大祭」はその日をしのぶ行事として全国の稲荷神社で行われます。
京都ではその日に「畑菜の辛し和え」を食べる習慣があるのです。ではなぜ、稲荷大社のお祭りである初午の日に畑菜なのか。実は、稲荷大社を祀ったのが「秦(はた)氏」であり、その「秦(はた)」と「畑(はたけ)菜」をかけているといわれています。また、畑菜は稲荷大社のシンボルである狐の大好物の油揚げと一緒に炊いても美味しいものです。
稲荷大社と秦氏と畑菜・・・上のような関係があるようですが、事実、京都では初午の日に畑菜を食べることは昔からの習慣となっています。また実際に、一年で一番寒くなるこの時期の畑菜は実に美味しいものなのです。今や菜っ葉類の野菜であれば小松菜など色鮮やかな濃い「緑色」が好まれ、見た目に少し黄色がかった畑菜は敬遠されがちです。ですが、京都の底冷えのする寒さにさらされた畑菜は、寒さによって葉の色を少し黄色くさせるもので、朝霜にあたることで美味しさと柔らかさを増させます。
一月の中旬から二月の話題で少し先走りすぎていますが、畑菜そのものはすでに出荷されており、店頭にも並んでいます。まず、ご賞味いただき、初午の日にぜひもう一度、味わってくださいませ。

**************************
市場にはまだ出荷されています。
初午に限らず、寒い日には畑菜が一段と美味しくなります。
ぜひ、お試しを・・・。
http://kyoyasai.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=424581&csid=1
京にんじん も販売しています。
からし菜ご入用でしたらご連絡を・・・。
もちろん、九条ねぎ・みず菜ももちろんあります・・・。
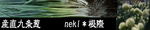
今回は第2回目。
1月に書いた記事ですが、紹介しているモノは「畑菜」です。^^
そう、京都では「初午」のときに食べる野菜です。
このブログでも取り上げています。。
⇒http://kyoyasai.seesaa.net/article/83112638.html
⇒http://kyoyasai.seesaa.net/article/83452943.html
では・・・・
**************************
京の菜時記 (畑菜)
みなさん、おめでとうございます。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、今回で二回目となります。さて、今回ご紹介する野菜は少し珍しい葉モノ野菜・・・「畑菜」です。
そもそも菜種油をとるために栽培されてきた京都の冬の代表的な葉モノ野菜ですが、なぜ一月の新年号に畑菜を紹介させていただくかというと、わけがございます。一年で畑菜を最もよく食べるという日あるのです。それが今年は二月六日。是非、その日に畑菜を食べていただきたく、一月の今号にご紹介させていただきます。
さて、みなさん、伏見稲荷神社をご存知でしょうか。全国の稲荷神社の総本社としてあまりにも有名な伏見稲荷大社ですが、二月の最初の午の日に行われる行事があるのです。それが、「初午大祭」。和銅四年(711年)、稲荷山の三ヶ峰に稲荷大神が初めてご鎮座された日が、二月の初午の日・・・といわれており、「初午大祭」はその日をしのぶ行事として全国の稲荷神社で行われます。
京都ではその日に「畑菜の辛し和え」を食べる習慣があるのです。ではなぜ、稲荷大社のお祭りである初午の日に畑菜なのか。実は、稲荷大社を祀ったのが「秦(はた)氏」であり、その「秦(はた)」と「畑(はたけ)菜」をかけているといわれています。また、畑菜は稲荷大社のシンボルである狐の大好物の油揚げと一緒に炊いても美味しいものです。
稲荷大社と秦氏と畑菜・・・上のような関係があるようですが、事実、京都では初午の日に畑菜を食べることは昔からの習慣となっています。また実際に、一年で一番寒くなるこの時期の畑菜は実に美味しいものなのです。今や菜っ葉類の野菜であれば小松菜など色鮮やかな濃い「緑色」が好まれ、見た目に少し黄色がかった畑菜は敬遠されがちです。ですが、京都の底冷えのする寒さにさらされた畑菜は、寒さによって葉の色を少し黄色くさせるもので、朝霜にあたることで美味しさと柔らかさを増させます。
一月の中旬から二月の話題で少し先走りすぎていますが、畑菜そのものはすでに出荷されており、店頭にも並んでいます。まず、ご賞味いただき、初午の日にぜひもう一度、味わってくださいませ。

**************************
市場にはまだ出荷されています。
初午に限らず、寒い日には畑菜が一段と美味しくなります。
ぜひ、お試しを・・・。
http://kyoyasai.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=424581&csid=1
京にんじん も販売しています。
からし菜ご入用でしたらご連絡を・・・。
もちろん、九条ねぎ・みず菜ももちろんあります・・・。
2010年02月22日
京の菜時記 (頭芋)
今更な話ですが、私、京野菜集荷業とともに社会保険労務士を営んでおります。
一昨年から、とある任意団体に参加させていただいており、毎月1回の無料相談にもださせていただいております。
行政書士さんが中心で、相談者と私たちのような士業が気軽にお話ができるような場(関係)をということで設立された団体です。
その関係作りの一つとして「はあとメール」という定期冊子を毎月発行し、相談にこられて承諾を得た方に発送しております。
その中で、「京の菜時記」という原稿を書かせていただいており、今月で足掛け15回目(発行は18回目)となりました。
不定期ではありますが、その原稿を少しづつ小出しにご紹介させていただきます。
**************************
「京の菜時記 (頭芋)」
みなさんはじめまして。今回より記事を書かせていただくことになりましたはあとメールの橋本將詞(社会保険労務士)です。
はあとメールは「市民と法律家(専門家)の、文通による双方向の交流」を目的としたものです。私からは法律以外の話で少し箸休めをしていただこうと京都の旬な野菜のお話をさせていただきます。どうぞ私の話・・・そして野菜を通じて季節を感じていただければ幸いです。題して、「京の菜時記」。
さて、今年も残りわずか。少し気は早いですが、京都中央市場にはすでにお正月用の野菜が並びだしています。「京くわい」や「金時人参」、「堀川ごぼう」「海老芋」「聖護院大根」など、京都の冬野菜は色とりどりです。そんな中、今回は京都のお正月に欠かすことができない「頭芋(カシライモ)」をご紹介します。
お正月といえば、お雑煮。京都のお雑煮は白味噌に丸餅、そしてお椀の中で一際自己主張する物体、それが頭芋です。頭芋は、京都のお雑煮に欠かすことができないもので、お正月前の今の時期しか店頭には並びません。6月に種芋を植え、夏は畝の間に水を張り、手間隙かけて作られた芋は、10月下旬から11月上旬にかけて掘り起こされます。そして12月の出荷時期まで土の中に埋められて、根を腐らせ、芽を伸ばし、一つ一つ丁寧に掃除して選別し出荷され、種芋から約半年かけて店頭に。
芽が出ているところから縁起がいいとされ、また「頭」という名前から一家の大黒柱には一番大きなものを盛り付けるともいわれています。そういう縁起物という云われがある一方で、もち米が高価なものであったとされるその昔、餅の代わりに食感が似ている頭芋を代用した・・・という話しもあります。
ただ、あまりに大きい頭芋を椀一杯に盛り付けられるとそれだけでお腹が一杯になってしまい、肝心のおせち料理が食べられないとの噂も・・・。
頭芋を作られている生産者の方は、「雑煮に入れるよりも小芋と同じように油揚げと大根で炊いて食べるほうが美味しい」と話されます。実は、私もそう思います。
京都には店頭をにぎわす四季折々の野菜が並びます。頭芋は年末・正月を感じさせる京都の野菜です。皆さんもぜひ、味わってみてください。

****************************
少し時期がづれてしまいましたが、春先に書いた花菜や分葱のことまで駆け足でご紹介します。
本日は、第1回目で「頭芋」でした。。^^
http://kyoyasai.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=424581&csid=1
京にんじん も販売しています。
からし菜ご入用でしたらご連絡を・・・。
もちろん、九条ねぎ・みず菜ももちろんあります・・・。
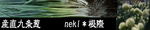
一昨年から、とある任意団体に参加させていただいており、毎月1回の無料相談にもださせていただいております。
行政書士さんが中心で、相談者と私たちのような士業が気軽にお話ができるような場(関係)をということで設立された団体です。
その関係作りの一つとして「はあとメール」という定期冊子を毎月発行し、相談にこられて承諾を得た方に発送しております。
その中で、「京の菜時記」という原稿を書かせていただいており、今月で足掛け15回目(発行は18回目)となりました。
不定期ではありますが、その原稿を少しづつ小出しにご紹介させていただきます。
**************************
「京の菜時記 (頭芋)」
みなさんはじめまして。今回より記事を書かせていただくことになりましたはあとメールの橋本將詞(社会保険労務士)です。
はあとメールは「市民と法律家(専門家)の、文通による双方向の交流」を目的としたものです。私からは法律以外の話で少し箸休めをしていただこうと京都の旬な野菜のお話をさせていただきます。どうぞ私の話・・・そして野菜を通じて季節を感じていただければ幸いです。題して、「京の菜時記」。
さて、今年も残りわずか。少し気は早いですが、京都中央市場にはすでにお正月用の野菜が並びだしています。「京くわい」や「金時人参」、「堀川ごぼう」「海老芋」「聖護院大根」など、京都の冬野菜は色とりどりです。そんな中、今回は京都のお正月に欠かすことができない「頭芋(カシライモ)」をご紹介します。
お正月といえば、お雑煮。京都のお雑煮は白味噌に丸餅、そしてお椀の中で一際自己主張する物体、それが頭芋です。頭芋は、京都のお雑煮に欠かすことができないもので、お正月前の今の時期しか店頭には並びません。6月に種芋を植え、夏は畝の間に水を張り、手間隙かけて作られた芋は、10月下旬から11月上旬にかけて掘り起こされます。そして12月の出荷時期まで土の中に埋められて、根を腐らせ、芽を伸ばし、一つ一つ丁寧に掃除して選別し出荷され、種芋から約半年かけて店頭に。
芽が出ているところから縁起がいいとされ、また「頭」という名前から一家の大黒柱には一番大きなものを盛り付けるともいわれています。そういう縁起物という云われがある一方で、もち米が高価なものであったとされるその昔、餅の代わりに食感が似ている頭芋を代用した・・・という話しもあります。
ただ、あまりに大きい頭芋を椀一杯に盛り付けられるとそれだけでお腹が一杯になってしまい、肝心のおせち料理が食べられないとの噂も・・・。
頭芋を作られている生産者の方は、「雑煮に入れるよりも小芋と同じように油揚げと大根で炊いて食べるほうが美味しい」と話されます。実は、私もそう思います。
京都には店頭をにぎわす四季折々の野菜が並びます。頭芋は年末・正月を感じさせる京都の野菜です。皆さんもぜひ、味わってみてください。

****************************
少し時期がづれてしまいましたが、春先に書いた花菜や分葱のことまで駆け足でご紹介します。
本日は、第1回目で「頭芋」でした。。^^
http://kyoyasai.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=424581&csid=1
京にんじん も販売しています。
からし菜ご入用でしたらご連絡を・・・。
もちろん、九条ねぎ・みず菜ももちろんあります・・・。


