2010年09月16日
ねぎ苗
お昼前に九条ねぎの苗の掃除をされている生産者がおられたので寄ってきました。

これが干した後のねぎ。
先の部分を切り落とし、畝に定植します。

干すことでらっきょに養分が溜まり、美味しいねぎとなります。
植えるときの注意点。

このように苗の時点で葉が伸びる本数が上からみるとわかります。(分結はしますが・・・・)
定植するときは苗を数本束ねてされますので、そのときに伸びる葉の数を見ながらなれるそうです。
でも、今の時期にこの作業・・・・。
通常なら、苗植えが終わっているのに・・・・。
この暑さ・・・、全てが狂ってきます。
それに、おっちゃんが話されていましたが、干してあるねぎを盗む輩がいるとか・・・。1反分も盗まれた生産者もおられると聞きます。
全てが狂ってる・・・・。
上鳥羽の生産者が作る京野菜の情報をご希望の方は、ぜひご連絡ください。
なお、情報は不定期に発送するものです。ご希望によってDMもしくはFAX、またはメール、電話。
お問合せはこちらから
TEL/FAX 075-693-6757
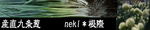

これが干した後のねぎ。
先の部分を切り落とし、畝に定植します。

干すことでらっきょに養分が溜まり、美味しいねぎとなります。
植えるときの注意点。

このように苗の時点で葉が伸びる本数が上からみるとわかります。(分結はしますが・・・・)
定植するときは苗を数本束ねてされますので、そのときに伸びる葉の数を見ながらなれるそうです。
でも、今の時期にこの作業・・・・。
通常なら、苗植えが終わっているのに・・・・。
この暑さ・・・、全てが狂ってきます。
それに、おっちゃんが話されていましたが、干してあるねぎを盗む輩がいるとか・・・。1反分も盗まれた生産者もおられると聞きます。
全てが狂ってる・・・・。
上鳥羽の生産者が作る京野菜の情報をご希望の方は、ぜひご連絡ください。
なお、情報は不定期に発送するものです。ご希望によってDMもしくはFAX、またはメール、電話。
お問合せはこちらから
TEL/FAX 075-693-6757
2010年09月14日
京の菜時記(伏見甘長)
京の菜時記、第8回目。
月一回の発行で、本日載せる記事は8月号でしょうか。。
============================================================================
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、8回目となります今回は、伏見とうがらしをご紹介します。
トウガラシは、熱帯アメリカ原産で約6000年前の遺跡から出土するなど相当昔から食されていたようです。日本には、豊臣秀吉の時代に朝鮮半島から伝わり、その当時「高麗胡椒(コショウ)」と呼んでいたという説と、ポルトガル人がブラジルより日本にもたらしたという説もあるようですが、いずれにしても同時代に日本に広まったと考えられています。ただ、その頃に伝来したトウガラシは「胡椒」の名でもわかるように香辛料として用途されていたようで、江戸時代に全国各地作られるようになってもなお辛味の強いものでした。
また、唐辛子と同じ仲間ながら辛味のまったくないピーマンは未だその頃には日本になかったといわれています。
そんな全国各地で作られるようになったトウガラシの中の一つに、伏見とうがらしは生まれました。「雍州府志」(1684)に山城の稲荷付近で作られていたと記載があり、それ以前より京都伏見辺りで栽培されており、その地名をとって「伏見とうがらし」と名づけられました。別名「伏見甘長とうがらし」と呼ばれるように、形状は細長く10cm~20cm近いものもあり、辛味はありません。(何度も食していますが、辛いものに当たったことがありません。)焼いて少し焦げ目を付け、醤油で食べるのが一般的ですが、天ぷらにしても、葉とともにちりめん雑魚と炊いて佃煮風にしても美味しくいただけます。
今のように京野菜ブランドが確立する以前は作付面積が減る一方で、出荷量も少なくなりましたが、今では京都府域各地で栽培されており、ハウス等の施設栽培によって年間通じて食べることができるようになりました。ですが、旬の時期としてはやはり夏(6月~8月)。冬の寒い時期に暖房を焚いたハウス内で栽培されるモノを食べるよりも、自然の太陽の光を直接浴びた路地モノが出回る今の時期をお勧めします。施設栽培では、流通量に限りがありコストがかかるため価格が高くなりがちです。
食物繊維・カルシウム等が豊富で夏バテ防止の京野菜ですので、是非どうぞ。

================================================================================
上鳥羽の生産者が作る京野菜の情報をご希望の方は、ぜひご連絡ください。
なお、情報は不定期に発送するものです。ご希望によってDMもしくはFAX、またはメール、電話。
お問合せはこちらから
TEL/FAX 075-693-6757
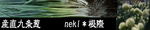
月一回の発行で、本日載せる記事は8月号でしょうか。。
============================================================================
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、8回目となります今回は、伏見とうがらしをご紹介します。
トウガラシは、熱帯アメリカ原産で約6000年前の遺跡から出土するなど相当昔から食されていたようです。日本には、豊臣秀吉の時代に朝鮮半島から伝わり、その当時「高麗胡椒(コショウ)」と呼んでいたという説と、ポルトガル人がブラジルより日本にもたらしたという説もあるようですが、いずれにしても同時代に日本に広まったと考えられています。ただ、その頃に伝来したトウガラシは「胡椒」の名でもわかるように香辛料として用途されていたようで、江戸時代に全国各地作られるようになってもなお辛味の強いものでした。
また、唐辛子と同じ仲間ながら辛味のまったくないピーマンは未だその頃には日本になかったといわれています。
そんな全国各地で作られるようになったトウガラシの中の一つに、伏見とうがらしは生まれました。「雍州府志」(1684)に山城の稲荷付近で作られていたと記載があり、それ以前より京都伏見辺りで栽培されており、その地名をとって「伏見とうがらし」と名づけられました。別名「伏見甘長とうがらし」と呼ばれるように、形状は細長く10cm~20cm近いものもあり、辛味はありません。(何度も食していますが、辛いものに当たったことがありません。)焼いて少し焦げ目を付け、醤油で食べるのが一般的ですが、天ぷらにしても、葉とともにちりめん雑魚と炊いて佃煮風にしても美味しくいただけます。
今のように京野菜ブランドが確立する以前は作付面積が減る一方で、出荷量も少なくなりましたが、今では京都府域各地で栽培されており、ハウス等の施設栽培によって年間通じて食べることができるようになりました。ですが、旬の時期としてはやはり夏(6月~8月)。冬の寒い時期に暖房を焚いたハウス内で栽培されるモノを食べるよりも、自然の太陽の光を直接浴びた路地モノが出回る今の時期をお勧めします。施設栽培では、流通量に限りがありコストがかかるため価格が高くなりがちです。
食物繊維・カルシウム等が豊富で夏バテ防止の京野菜ですので、是非どうぞ。

================================================================================
上鳥羽の生産者が作る京野菜の情報をご希望の方は、ぜひご連絡ください。
なお、情報は不定期に発送するものです。ご希望によってDMもしくはFAX、またはメール、電話。
お問合せはこちらから
TEL/FAX 075-693-6757
2010年09月13日
京の菜時記(賀茂茄子)
京の菜時記
油断をしていたら、時期がずれてしまいました。
もうすぐ終わりですが、この野菜を・・・・
=============================================================
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、7回目となります今回は、京野菜を代表する野菜、賀茂茄子をご紹介します。
賀茂茄子の起源については明らかではありませんが、1684年刊行の「雍州府志」という書物に洛東河原において栽培していた丸くて大きい茄子という記述があり、これが賀茂茄子だといわれています。栽培の上で多量の水を要すため、水利に恵まれた地区が産地となり、京都市内では上賀茂・西賀茂周辺が主な産地です。現在では、京都府綾部市や亀岡市でも盛んに栽培されています。ただ、市場価格・店頭価格について、京都産は少々高くなっております。近畿圏では、奈良県でも丸茄子として出荷されており、京都の量販店でも購入することができます。
手にあまる大きさで、直径は15cm、重さは1k近くあるものも。ですが、近年は比較的小さなものが多くなっています。というのにもわけがあり、料理店にあっては、あまりに大きな賀茂茄子を懐石料理の一つとして出すと、それ一つでお腹がいっぱいになってしまう。また、スーパー等の量販店からも小さいほうが消費者に手ごろ感があるとのことで、綾部市や亀岡市の賀茂茄子は比較的小さめのサイズを多くなっています。一方、昔からの産地である上賀茂・西賀茂の生産者の方は、賀茂茄子にはこのズッシリ感がないと・・・とおっしゃられ、見事なまでの大きくて立派な賀茂茄子を作られておられます。茄子は、1本の木から数十本が収穫できますが、賀茂茄子は花を落とし選定する作業に手間がかかります。大きなものを作るにはなおの事、一つの実に栄養分を集中させるためにもったいないと思えるほど選定し、花のうちに落としてしまいます。そのようにして、立派な賀茂茄子が収穫されるのです。
賀茂茄子には、「三ヘタ」といって三角形のヘタが特徴で、またそこには大きなトゲがあり、そのトゲに触れると痛いこと。表面を覆う皮は柔らかく、キズがつければそこから傷みはじめるために、収穫・出荷には細心の注意が必要です。
上賀茂の生産者といえば、昔ながらの振り売りで有名です。今でも多品目の野菜を売りに回っておられます。そのために、京都市産に限れば市場を介しての流通量は極端に少なく、また貴重な野菜といえます。

===================================================================
上鳥羽の生産者が作る京野菜の情報をご希望の方は、ぜひご連絡ください。
なお、情報は不定期に発送するものです。ご希望によってDMもしくはFAX、またはメール、電話。
お問合せはこちらから
TEL/FAX 075-693-6757
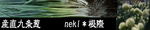
油断をしていたら、時期がずれてしまいました。
もうすぐ終わりですが、この野菜を・・・・
=============================================================
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、7回目となります今回は、京野菜を代表する野菜、賀茂茄子をご紹介します。
賀茂茄子の起源については明らかではありませんが、1684年刊行の「雍州府志」という書物に洛東河原において栽培していた丸くて大きい茄子という記述があり、これが賀茂茄子だといわれています。栽培の上で多量の水を要すため、水利に恵まれた地区が産地となり、京都市内では上賀茂・西賀茂周辺が主な産地です。現在では、京都府綾部市や亀岡市でも盛んに栽培されています。ただ、市場価格・店頭価格について、京都産は少々高くなっております。近畿圏では、奈良県でも丸茄子として出荷されており、京都の量販店でも購入することができます。
手にあまる大きさで、直径は15cm、重さは1k近くあるものも。ですが、近年は比較的小さなものが多くなっています。というのにもわけがあり、料理店にあっては、あまりに大きな賀茂茄子を懐石料理の一つとして出すと、それ一つでお腹がいっぱいになってしまう。また、スーパー等の量販店からも小さいほうが消費者に手ごろ感があるとのことで、綾部市や亀岡市の賀茂茄子は比較的小さめのサイズを多くなっています。一方、昔からの産地である上賀茂・西賀茂の生産者の方は、賀茂茄子にはこのズッシリ感がないと・・・とおっしゃられ、見事なまでの大きくて立派な賀茂茄子を作られておられます。茄子は、1本の木から数十本が収穫できますが、賀茂茄子は花を落とし選定する作業に手間がかかります。大きなものを作るにはなおの事、一つの実に栄養分を集中させるためにもったいないと思えるほど選定し、花のうちに落としてしまいます。そのようにして、立派な賀茂茄子が収穫されるのです。
賀茂茄子には、「三ヘタ」といって三角形のヘタが特徴で、またそこには大きなトゲがあり、そのトゲに触れると痛いこと。表面を覆う皮は柔らかく、キズがつければそこから傷みはじめるために、収穫・出荷には細心の注意が必要です。
上賀茂の生産者といえば、昔ながらの振り売りで有名です。今でも多品目の野菜を売りに回っておられます。そのために、京都市産に限れば市場を介しての流通量は極端に少なく、また貴重な野菜といえます。

===================================================================
上鳥羽の生産者が作る京野菜の情報をご希望の方は、ぜひご連絡ください。
なお、情報は不定期に発送するものです。ご希望によってDMもしくはFAX、またはメール、電話。
お問合せはこちらから
TEL/FAX 075-693-6757
2010年09月10日
京にんじんの実は・・・
ちょっと必要があり、金時人参のデータをまとめたので以下に載せます。
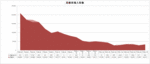
これは、京都中央卸売市場に入荷する京都府内産の金時人参の推移です。
色の濃い部分が京都市内産。
それ以外の薄い部分が京都市以外・・・京都府内です。
京都市内がほとんどを占めています。京都市内=(おおよそ)上鳥羽産です。
すごいでしょ。。
ということが言いたいのではなく、入荷量の減り方です。
20年前に比べて約6分の1に減少していることが一目瞭然。
私が仕事をし始めた平成7年当時でも平成元年に比べて半減。当時で12月初旬から毎日400ケース程度運んでいました。
それが今では12月の特定の週だけ日に100ケース程度。
これだけ減少しているわけです。
価値があがったので、価格も上っている・・・。
と考えるのは大間違い。
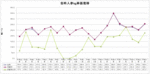
実は、k単価は昔とそれほど変わっていません。
ということは、作付けが増えれば、需要が上らないことには、その分下がるということ。
何度も何度も申していますが、京人参とよばれる「真っ赤」な「甘み」と「香り」のある金時人参は上鳥羽の土壌でしか作ることができません。市場の評価はともかく、一度使ってみて評価ください。
一度使えば、上鳥羽の京人参しか使えなくなります。
(有名料理長談)
出荷はまだまだ先ですが、間引きの人参葉がもうそろそろです。。。
上鳥羽の生産者が作る京野菜の情報をご希望の方は、ぜひご連絡ください。
なお、情報は不定期に発送するものです。ご希望によってDMもしくはFAX、またはメール、電話。
お問合せはこちらから
TEL/FAX 075-693-6757
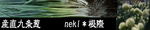
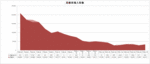
これは、京都中央卸売市場に入荷する京都府内産の金時人参の推移です。
色の濃い部分が京都市内産。
それ以外の薄い部分が京都市以外・・・京都府内です。
京都市内がほとんどを占めています。京都市内=(おおよそ)上鳥羽産です。
すごいでしょ。。
ということが言いたいのではなく、入荷量の減り方です。
20年前に比べて約6分の1に減少していることが一目瞭然。
私が仕事をし始めた平成7年当時でも平成元年に比べて半減。当時で12月初旬から毎日400ケース程度運んでいました。
それが今では12月の特定の週だけ日に100ケース程度。
これだけ減少しているわけです。
価値があがったので、価格も上っている・・・。
と考えるのは大間違い。
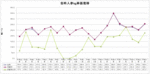
実は、k単価は昔とそれほど変わっていません。
ということは、作付けが増えれば、需要が上らないことには、その分下がるということ。
何度も何度も申していますが、京人参とよばれる「真っ赤」な「甘み」と「香り」のある金時人参は上鳥羽の土壌でしか作ることができません。市場の評価はともかく、一度使ってみて評価ください。
一度使えば、上鳥羽の京人参しか使えなくなります。
(有名料理長談)
出荷はまだまだ先ですが、間引きの人参葉がもうそろそろです。。。
上鳥羽の生産者が作る京野菜の情報をご希望の方は、ぜひご連絡ください。
なお、情報は不定期に発送するものです。ご希望によってDMもしくはFAX、またはメール、電話。
お問合せはこちらから
TEL/FAX 075-693-6757
2010年09月06日
かもうり
昨日の話(おっちゃんが冬瓜を鴨瓜と呼んでいた話)ですが、ネットで調べてみると、冬瓜は江戸時代からの呼称で、奈良時代(?)の書物にて「かもうり」との記述があるそうです。
ふぇ~~~、ほんまに「かもうり」っていうてたんですね。

さすが・・・・・・おっちゃんが言われるとおり、そんな昔から「かもうり」と呼んでいたなら理由も何もわからないはず・・・。
80代のおっちゃんが生まれる遥か前から「かもうり」で通っていたんですから。
漢字では「氈瓜」このように書くようです。
へぇ~~~、そんな歴史ある野菜だったんですね。。
上鳥羽の生産者が作る京野菜の情報をご希望の方は、ぜひご連絡ください。
なお、情報は不定期に発送するものです。ご希望によってDMもしくはFAX、またはメール、電話。
お問合せはこちらから
TEL/FAX 075-693-6757
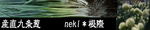
ふぇ~~~、ほんまに「かもうり」っていうてたんですね。

さすが・・・・・・おっちゃんが言われるとおり、そんな昔から「かもうり」と呼んでいたなら理由も何もわからないはず・・・。
80代のおっちゃんが生まれる遥か前から「かもうり」で通っていたんですから。
漢字では「氈瓜」このように書くようです。
へぇ~~~、そんな歴史ある野菜だったんですね。。
上鳥羽の生産者が作る京野菜の情報をご希望の方は、ぜひご連絡ください。
なお、情報は不定期に発送するものです。ご希望によってDMもしくはFAX、またはメール、電話。
お問合せはこちらから
TEL/FAX 075-693-6757
2010年09月05日
「ずいき」と「冬瓜」
出荷状況・・・というわけではありませんが、この時期に収穫する「ずいき」と「冬瓜」をご紹介。
「ずいき」は何度も書いてます。
上鳥羽では京都の雑煮に欠かせない頭芋の生産が盛んです。
6月に種芋を植え、水をたやさず張り続け、今の時期は「ずいき」(芋茎)がもっとも元気のいい時期です。
こんな感じ。。

立ててみると・・・

こんなにも太くなっています。
赤ずいきとして今の時期店頭に並ぶものと比べても太さは一目瞭然。
調理するには細いほうが好まれますが、味や食感は太いほうがいい(・・・と個人的には)思います。ただ、食べる前の準備が結構な手間です。
切るのも大変、皮を剥くのも大変。
この元気な芋茎の養分がどんどんと芋にたまっていきます。。。
頭芋の今の状態は・・・・

まだ、茎の一部という感じ。
切り口も・・・・

これが12月にはこんな感じになります。

はてさて、もう一つの冬瓜ですが、特大サイズを・・・

見事な冬瓜です。
そぼろあんかけにして食べると格別。
上鳥羽の生産者から冬瓜のことを「かも瓜」(・・・鴨瓜?)と呼んでいたとお聞きしました。恩歳83歳の大ベテランのおっちゃんです。
おっちゃんが子供の頃?百姓はじめた頃?はそう呼んでいたそうです。
何かいわれがあるのかな??
ちょっと調べてみる価値ありかも。。。
上鳥羽の生産者が作る京野菜の情報をご希望の方は、ぜひご連絡ください。
なお、情報は不定期に発送するものです。ご希望によってDMもしくはFAX、またはメール、電話。
お問合せはこちらから
TEL/FAX 075-693-6757
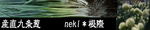
「ずいき」は何度も書いてます。
上鳥羽では京都の雑煮に欠かせない頭芋の生産が盛んです。
6月に種芋を植え、水をたやさず張り続け、今の時期は「ずいき」(芋茎)がもっとも元気のいい時期です。
こんな感じ。。

立ててみると・・・

こんなにも太くなっています。
赤ずいきとして今の時期店頭に並ぶものと比べても太さは一目瞭然。
調理するには細いほうが好まれますが、味や食感は太いほうがいい(・・・と個人的には)思います。ただ、食べる前の準備が結構な手間です。
切るのも大変、皮を剥くのも大変。
この元気な芋茎の養分がどんどんと芋にたまっていきます。。。
頭芋の今の状態は・・・・

まだ、茎の一部という感じ。
切り口も・・・・

これが12月にはこんな感じになります。

はてさて、もう一つの冬瓜ですが、特大サイズを・・・

見事な冬瓜です。
そぼろあんかけにして食べると格別。
上鳥羽の生産者から冬瓜のことを「かも瓜」(・・・鴨瓜?)と呼んでいたとお聞きしました。恩歳83歳の大ベテランのおっちゃんです。
おっちゃんが子供の頃?百姓はじめた頃?はそう呼んでいたそうです。
何かいわれがあるのかな??
ちょっと調べてみる価値ありかも。。。
上鳥羽の生産者が作る京野菜の情報をご希望の方は、ぜひご連絡ください。
なお、情報は不定期に発送するものです。ご希望によってDMもしくはFAX、またはメール、電話。
お問合せはこちらから
TEL/FAX 075-693-6757


