2010年03月23日
京にんじんの販売を終了します。。
春が近づくにつれ、冬野菜が終了にむかっています。
冬野菜がメインとなる上鳥羽としては寂しい限り・・・。
現時点(平成22年3月23日)では、まだ出荷はあるものの、生産者が納得できなければ出荷をさせていただくことができませんので、少し早いのですが、「京にんじん」の販売を終了させていただきます。
どうしても必要・・・という方がおられればご連絡ください。
京筍のほか、上鳥羽の生産者が作るもの以外の京野菜各種を、京都中央市場から直接仕入れにて対応することができます。ぜひ、ご相談ください。
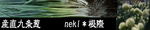
冬野菜がメインとなる上鳥羽としては寂しい限り・・・。
現時点(平成22年3月23日)では、まだ出荷はあるものの、生産者が納得できなければ出荷をさせていただくことができませんので、少し早いのですが、「京にんじん」の販売を終了させていただきます。
どうしても必要・・・という方がおられればご連絡ください。
京筍のほか、上鳥羽の生産者が作るもの以外の京野菜各種を、京都中央市場から直接仕入れにて対応することができます。ぜひ、ご相談ください。
2010年03月13日
京の菜時記~筍~
このままいけば、少し季節を追い越す感はありますが、筍の菜時記を・・・・。
**************************
京の菜時記 (筍)
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、今回は春を代表する野菜としてあまりにも有名な「京たけのこ」を紹介します。
さて、春の味覚といえば「筍」。筍は名前の通り「竹の子」ですが一般的には「孟宗竹」という種類を食します。孟宗竹は中国から伝来したもので、その時期等については諸説あります。800年代に京都府長岡京市にある寂照院の開祖が唐から持ち帰り植えたという説があり、境内の入り口には「日本孟宗竹発祥の地」の石碑が建っています。
筍そのものは全国各地で作られていますが、京都の筍は、光るような白さと軟らかさ、そして何ともいえない独特の風味が特徴で、それらは毎年行われる「土入れ」「敷わら」という生産者の努力の賜物でもあり、長年の経験を要するものでもあります。
筍は当然のことながら竹林で栽培します。「土入れ」と一言でいってもその作業は大変なもので、足場の悪い竹林を、土をいっぱいにもった手押し車で何度も何度も往復するという極めて大変な作業です。また収穫時は、地表から芽をだしてしまうと色がすぐに変わってしまうために、竹林中を歩いて周り、地表に出ていない芽を見つけるという相当な経験と、折れないように細心の注意を払い筍掘り専用の鍬をつかっての収穫するという熟練された技が必要なのです。
京都では、皮の色が白く軟らかい筍を「シロコ」といいます。「シロコ」は皮が薄くて肉質柔らか、市場評価も極めて高く、まさしく「これぞ、京たけのこ」です。京都では盆地を囲む各地の竹林で栽培はされていますが、「京たけのこ」の代表産地といえば、京都西山一帯(長岡京、乙訓、大原野等)が特に有名です。西山一帯では、今の時期は各地で朝掘り筍の直売がされており、春の味覚を味わおうとどこも盛況です。
筍料理といえば、ワカメとあっさりと炊いて筍の風味を引き立てる「若竹煮」。ワカメのとろとろ感と筍の歯ごたえ、ほのかに香ばしい香りが独特です。また、新鮮な筍は刺身としてわさび醤油で食べるのも粋なもの。筍御飯と筍づくしはいかがですか?

**************************
http://kyoyasai.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=424581&csid=1
京にんじん も販売しています。
京都の分葱ご入用でしたらご連絡を・・・。
もちろん、九条ねぎ・みず菜ももちろんあります・・・。
・・・っと、みず菜は終了しました。。
京筍は、市場仕入れで対応できます。
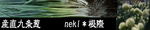
**************************
京の菜時記 (筍)
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、今回は春を代表する野菜としてあまりにも有名な「京たけのこ」を紹介します。
さて、春の味覚といえば「筍」。筍は名前の通り「竹の子」ですが一般的には「孟宗竹」という種類を食します。孟宗竹は中国から伝来したもので、その時期等については諸説あります。800年代に京都府長岡京市にある寂照院の開祖が唐から持ち帰り植えたという説があり、境内の入り口には「日本孟宗竹発祥の地」の石碑が建っています。
筍そのものは全国各地で作られていますが、京都の筍は、光るような白さと軟らかさ、そして何ともいえない独特の風味が特徴で、それらは毎年行われる「土入れ」「敷わら」という生産者の努力の賜物でもあり、長年の経験を要するものでもあります。
筍は当然のことながら竹林で栽培します。「土入れ」と一言でいってもその作業は大変なもので、足場の悪い竹林を、土をいっぱいにもった手押し車で何度も何度も往復するという極めて大変な作業です。また収穫時は、地表から芽をだしてしまうと色がすぐに変わってしまうために、竹林中を歩いて周り、地表に出ていない芽を見つけるという相当な経験と、折れないように細心の注意を払い筍掘り専用の鍬をつかっての収穫するという熟練された技が必要なのです。
京都では、皮の色が白く軟らかい筍を「シロコ」といいます。「シロコ」は皮が薄くて肉質柔らか、市場評価も極めて高く、まさしく「これぞ、京たけのこ」です。京都では盆地を囲む各地の竹林で栽培はされていますが、「京たけのこ」の代表産地といえば、京都西山一帯(長岡京、乙訓、大原野等)が特に有名です。西山一帯では、今の時期は各地で朝掘り筍の直売がされており、春の味覚を味わおうとどこも盛況です。
筍料理といえば、ワカメとあっさりと炊いて筍の風味を引き立てる「若竹煮」。ワカメのとろとろ感と筍の歯ごたえ、ほのかに香ばしい香りが独特です。また、新鮮な筍は刺身としてわさび醤油で食べるのも粋なもの。筍御飯と筍づくしはいかがですか?

**************************
http://kyoyasai.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=424581&csid=1
京にんじん も販売しています。
京都の分葱ご入用でしたらご連絡を・・・。
もちろん、九条ねぎ・みず菜ももちろんあります・・・。
・・・っと、みず菜は終了しました。。
京筍は、市場仕入れで対応できます。
2010年03月03日
京の菜時記 (分葱)
京の菜時記、4回目に投稿した記事は今の時期にピッタリのこの野菜。
「分葱」です。
「九条ねぎと何が違うの?」
という質問も聞こえそうですが、まったく別物です。
・・・といってしまえばそれまでですが、ねぎと違い分けつが非常に多く、成長がすぎると茎(?)が太くなるのではなく、らっきょうが張ります。
また、分葱といえば「てっぱい」(白味噌和え)ですが、九条ねぎとは食感がまったく違います。
個人的には、「てっぱい」はやはり「分葱」です。
**************************
京の菜時記 (分葱)
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、前回に引き続き今回も春の野菜をご紹介。
さて、今回は一般的にいう「京野菜」のご紹介ではありません。でも、京都産となるとこの春先の短い期間しか流通しない貴重な野菜のご紹介です。それは「分葱(ワケギ)」。全国的には広島県が最も生産量が多いそうですが、京都でも作付けされ出荷されています。京都では春先の今の時期に出荷のピークを迎えます。
分葱と聞かれてどんな料理を思い浮べますか?分葱といえば皆さん口をそろえておっしゃるのが「てっぱい」です。その語源は「鉄砲和え」がなまったものらしいのですが、わかりません。てっぱいそのものは讃岐地方の伝統料理で香川県では「フナ」を入れるようです。地域・・・家庭・・・それぞれに入れる具材は違うかと思いますが、私の家では・・白味噌と白ゴマ・・・それにイカと火にあぶった油揚げ、そして分葱。分葱の変わりに春に出回る若葱を使うこともありますが、葱より明らかに柔らかくシャキッという食感は分葱ならではのものです。
分葱と九条葱(特に、春に出回る若葱)は一見すると同じようにみえますが、まったくの別物。春の陽射しをうけてどんどんと太く長く成長する九条ねぎに対して、分葱は根に養分を溜め込みます。つまり、らっきょが大きくなるのです。
春先に出始める分葱・・・暖かい日が続くと一気にらっきょがはり、たちまち出荷できる状態ではなくなります。生産者にとっては赤葉の掃除がやりにくくなり、束にする作業がやりにくくなり、見た目にも悪く出荷を取りやめるということになるのです。
上のような事情から京都産の分葱の出荷は約1ヶ月程度。2月下旬から出始めますが寒冷遮をかけて出荷を早めているものです。暖かい日が続くと酢味噌の効いたサッパリとした「分葱のてっぱい」・・・食べたくなりませんか?
ぜひ、ご賞味あれ。

**************************
http://kyoyasai.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=424581&csid=1
京にんじん も販売しています。
京都の分葱ご入用でしたらご連絡を・・・。
もちろん、九条ねぎ・みず菜ももちろんあります・・・。
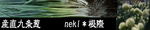
「分葱」です。
「九条ねぎと何が違うの?」
という質問も聞こえそうですが、まったく別物です。
・・・といってしまえばそれまでですが、ねぎと違い分けつが非常に多く、成長がすぎると茎(?)が太くなるのではなく、らっきょうが張ります。
また、分葱といえば「てっぱい」(白味噌和え)ですが、九条ねぎとは食感がまったく違います。
個人的には、「てっぱい」はやはり「分葱」です。
**************************
京の菜時記 (分葱)
みなさん、こんにちは。京の菜時記を書かせていただいております橋本將詞(社会保険労務士)です。毎回、京都でとれる旬の野菜を紹介しようと始めた「京の菜時記」、前回に引き続き今回も春の野菜をご紹介。
さて、今回は一般的にいう「京野菜」のご紹介ではありません。でも、京都産となるとこの春先の短い期間しか流通しない貴重な野菜のご紹介です。それは「分葱(ワケギ)」。全国的には広島県が最も生産量が多いそうですが、京都でも作付けされ出荷されています。京都では春先の今の時期に出荷のピークを迎えます。
分葱と聞かれてどんな料理を思い浮べますか?分葱といえば皆さん口をそろえておっしゃるのが「てっぱい」です。その語源は「鉄砲和え」がなまったものらしいのですが、わかりません。てっぱいそのものは讃岐地方の伝統料理で香川県では「フナ」を入れるようです。地域・・・家庭・・・それぞれに入れる具材は違うかと思いますが、私の家では・・白味噌と白ゴマ・・・それにイカと火にあぶった油揚げ、そして分葱。分葱の変わりに春に出回る若葱を使うこともありますが、葱より明らかに柔らかくシャキッという食感は分葱ならではのものです。
分葱と九条葱(特に、春に出回る若葱)は一見すると同じようにみえますが、まったくの別物。春の陽射しをうけてどんどんと太く長く成長する九条ねぎに対して、分葱は根に養分を溜め込みます。つまり、らっきょが大きくなるのです。
春先に出始める分葱・・・暖かい日が続くと一気にらっきょがはり、たちまち出荷できる状態ではなくなります。生産者にとっては赤葉の掃除がやりにくくなり、束にする作業がやりにくくなり、見た目にも悪く出荷を取りやめるということになるのです。
上のような事情から京都産の分葱の出荷は約1ヶ月程度。2月下旬から出始めますが寒冷遮をかけて出荷を早めているものです。暖かい日が続くと酢味噌の効いたサッパリとした「分葱のてっぱい」・・・食べたくなりませんか?
ぜひ、ご賞味あれ。

**************************
http://kyoyasai.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=424581&csid=1
京にんじん も販売しています。
京都の分葱ご入用でしたらご連絡を・・・。
もちろん、九条ねぎ・みず菜ももちろんあります・・・。


